インドにおけるトイレ建設の水質と健康に対する負の外部性(元橋ジョブマーケットペーパー)
新年明けましておめでとうございます!
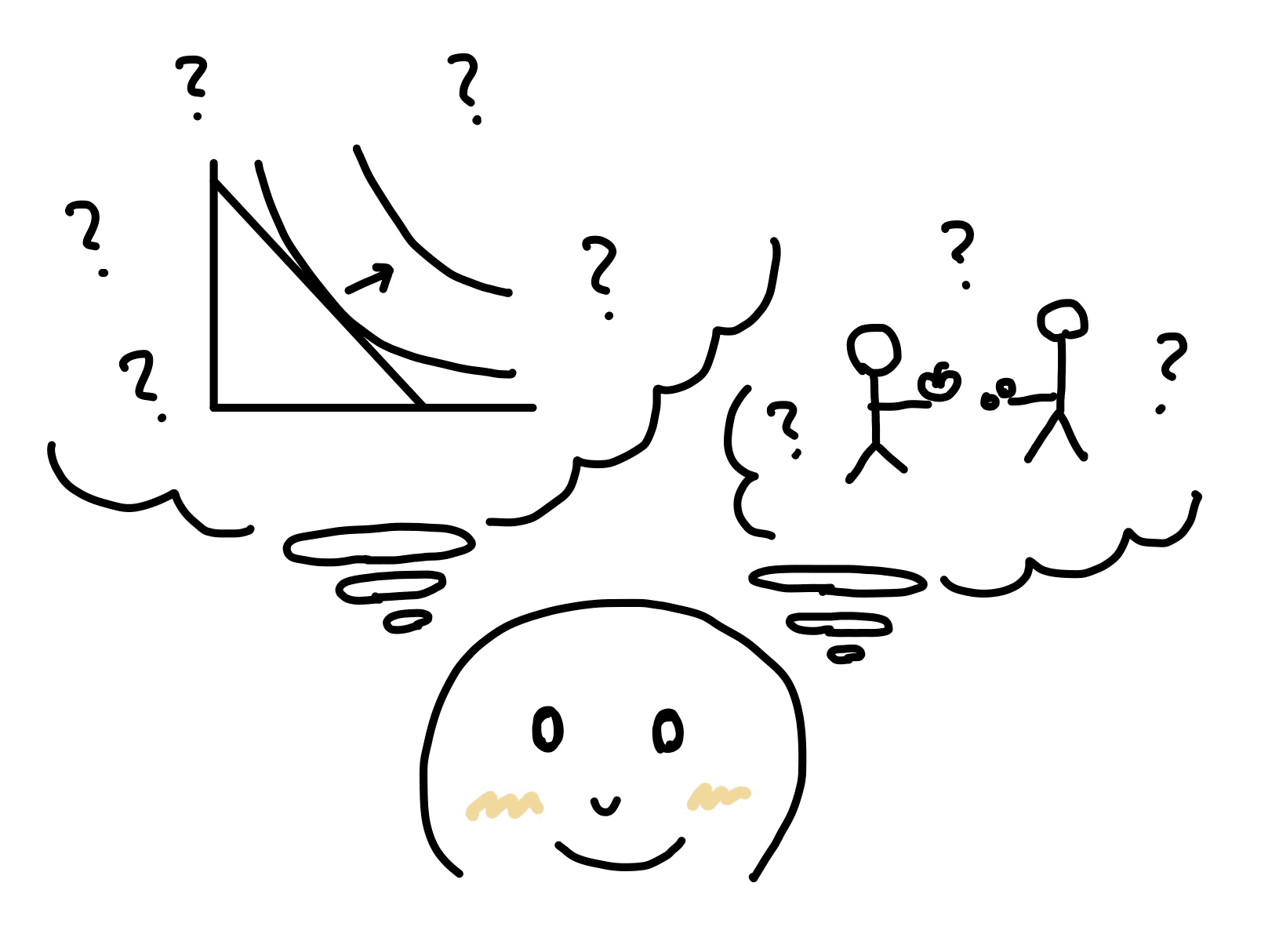
アメリカで勉強・研究する博士課程学生によるブログです。
新年明けましておめでとうございます!
皆さんこんにちは。先日の記事ではコロナウイルスワクチン忌避について考え、関係性のある文献という点から医療制度に対する不信の起源の研究を紹介しました。日本におけるコロナウイルスワクチン忌避率は国立精神神経医療研究センターの最新のインターネット調査では11%ほどと推定されています。また忌避以外にもワクチン接種意欲はあるのだけれども不便であったりその他の(供給以外の)制約があったりする場合、介入無しでは集団免疫と呼ばれるような社会的に十分なワクチン接種率にたどり着かない可能性も想定されます。
こんにちは!日本は梅雨まっただ中ですね。暑く湿気の高い日が続くようですが、皆さんお体にはお気をつけて!
皆さんこんにちは。コロナウイルスの感染第4波の中、日本でもワクチン接種のペースが6月中旬現在で1日平均70万回弱まで上昇してきています。今後の国内での感染拡大を防ぐためには少なくとも人口の大多数がワクチン接種などによる免疫取得が必要であると言われています(注:コロナウイルス 感染に関するリスクやワクチンに関する詳しい情報は厚生労働省などの公的機関からの情報をご確認ください)。過去数ヶ月はの輸入量の不足や配送の遅れなど供給側の問題が(特に1ヶ月後に迫ったオリンピックへの懸念とともに)目下の課題として取り上げられてきましたが、供給制約が緩和された国(アメリカやイスラエルなど)では、いまだに接種していない人々にどう接種を促すか(つまり受容側の問題)が課題となっています。日本もワクチンに対する不信感を抱く人々の割合が高いとされ、過去にも新三種混合(MMR)やHPVワクチンなどに対する副作用がメディアで大々的に取り上げられた結果、接種の推奨が中止され、子宮頸癌においては避けられたはずの患者や死者が発生するだろうとの研究も出ています。
ブログの記事の投稿が滞ってましたが、アメリカの大学では夏休みに入りましたので、これから記事をどんどんアップしていきます。ブログを放棄したわけではないため、これからの投稿を楽しみにしてください!
お久しぶりです!3月は(毎度ながら自分のせいですが)ちょっとキャパオーバーだったので勝手に臨時休業しました!w 4月からは気持ちを新たに継続的にブログと書くようにしていきたいと思います。(自分の勉強のためですしね。)
このブログの2月のテーマは「感染症、疫病」です(え、もう3月じゃんって?聞こえません)。 というわけで、今回は眠り病を媒介するツェツェバエがアフリカの発展にどのような影響を与えたかを研究した Alsan (2015)を紹介します。 ちなみに、私のお気に入りのYouTubeのチャンネル DeepLook にツェツェバエの動画があります(虫が苦手な方は無視してください)。
2月のテーマは「感染症、疫病」ということで、前回のジカウィルスに続き、今回はインフルエンザを取り上げます。
2月は1月の御目出度いトピック「祭り、慣習、宗教」から一転して、「感染症、疫病」と悲しいですが、タイムリーなテーマでブログを書いていきます。
このブログでは、1月は「祭り、慣習、宗教」に関連した論文を紹介しています。 興味がある方は、渋谷さんによるインドの結婚式に関する論文の紹介記事、元橋さんによるプロテスタントの医療伝道の長期的影響についての論文の紹介記事も合わせてご覧ください! 今回は、Montero and Yang による「宗教的なお祭りと経済発展の関係」についての論文を紹介します。 まだワーキングペーパーですが、論文はこちらでご覧になれます(PDF注意)。
新年明けましておめでとうございます! 1月のテーマは「祭り、慣習、宗教」ということで、 今回は、プロテスタントの宣教活動、健康の習慣等をテーマとした論文を取り上げます。CalviさんとMantovanelliさんさんによる“Long-term effects of access to health care: Medical missions in colonial India”です。
新年明けましておめでとうございます。昨年は私達のブログを読んでいただきありがとうございます。 今年も自分たちの学びを少しでも楽しく共有できたらとおもますので、よろしくお願いいたします。
今回は、シカゴ大のGreenstone先生とUCサンタバーバラ校のJack先生のレビュー論文“Envirodevonomics: A Research Agenda for an Emerging Field”について話したいと思います。
今年はコロナウイルス・パンデミックによりネットショッピング(Eコマース)やオンラインプラットフォームにおける経済活動が一層身近になりました。Eコマースの発達はもちろん先進国だけにとどまらず、途上国においても存在感を増してきています。私(中村)自身も、過去数年でライドシェアアプリや配達をフィールドワークの際使う機会が増え、数十円をかけてリキシャのおっちゃんと値切りバトルをしなくて良くなったのは便利だけれど少し寂しい気はします。携帯端末の普及により多様な人々が活動する様になった途上国におけるオンラインの市場でいかなるメカニズムが働き、どの様な摩擦、市場の失敗が存在するのか、というのが私の大まかな研究対象でもあるので、今回はBai et al. (2020)の”Search and Information Frictions on Global E-Commerce Platforms: Evidence from AliExpress”というワーキングペーパーを紹介します。直近のいろいろなところでのセミナーで発表されており、ワーキングペーパーはつい最近公開されたのでフレッシュな研究です。論文はこちらからダウンロードできます。
今日はFogliさんとVeldkampさんによる掲題の論文について話したいと思います。 論文はこちらから。
今回は「移住(permanent migration)とリスクシェアリング」をテーマにしたMunshi and Rosenzweig (2016)を紹介します。 この論文では「インドで都市・農村間の賃金差が大きいのはなぜ?」という疑問に対し「農村部でのリスクシェアリングのネットワークが発達しているため、人々が都市部に移住しない」という仮説をたて、モデルを構築し、その理論的予測をデータを用いて検証しています。
こんにちは。渋谷さん、鈴木さん、鈴木さんに続いて今回は私の経験に基づいた、経済学の博士号取得を考えている方向けの情報をまとめていこうと思います。今回は簡潔に自己紹介をした後、経済Ph Dプログラム出願において私が経験したリサーチアシスタント(いわゆるプレドクと呼ばれるポジション)についてまとめていこうと思います。日本語での情報が比較的少ない内容だと思うので、どなたかのお役に立てれば嬉しいです。
こんにちは。前回の鈴木さんの番外編に続き、今回は私(元橋)が経済学部・国際関係大学院(フレッチャースクール)の合同PhDプログラムで博士をするに至るまでの経緯についてお話したいと思います。私は学部のバックグランドが法学部で経済学に転換したタイプ+社会人経験を経た後のPhD留学なので、その経緯や苦労したことなどを共有できればと思います。
こんにちは。前回の渋谷さんの番外編に続き、今回は私(鈴木)が応用経済学部で博士をするに至るまでの経緯についてお話したいと思います。とはいうものの、どういう情報に需要があるのかよくわからないので、とりあえず「自分のしてきたことをざーっと書く」というスタイルを取ることにします。不必要な情報が多いでしょうが、それぞれで情報を取捨選択していただければと思います。もし追加で聞きたい情報があればこの記事にコメントを残す、econ.blog.japan@gmail.comまで連絡する、Twitterアカウント @EconJapan に連絡するなどの方法でコンタクトしていただければ、できる限りお答えします。
今日は Carter & Wilkinson (2013) “Food sharing in vampire bats: reciprocal help predicts donations more than relatedness or harassment”という論文を紹介します。はじめに断っておくと、これは経済学の論文ではありません。「ブログのコンセプトぶち壊しかよ!」という他のブログメンバーからの苦情が飛んできそうですが、無視することにします。 言い訳をすると、この論文では吸血コウモリの血を分け合う行動について分析しています。この研究を知ったときに開発経済学のトピックの一つである「リスクシェアリング」との関わりが深そうに感じ、両者の関係性を考えてみたいと思い今回の論文を選びました。
ブログ「経済学の研究を日本語で話す。」執筆者による座談会の第一回目を公開します!
こんにちは。今回は番外編として私(渋谷)が応用経済学部で博士をするに至るまでの経緯について簡単にお話したいと思います。
今日は、イェール大のJensenさんのQJE論文”The (perceived) returns to education and the demand for schooling”について話したいと思います。 論文はこちらからダウンロードできます。
今回はAbadie, Athey Imbens and Wooldridge (2017)(以下AAIW)についてお話します。とはいっても、ほとんど自分の勉強の為の備忘録といった内容で、すごくつまらないと思うので先に謝っておきます。
今回はBesley and Case (1994)を紹介します。 この論文は出版されていないものですが、「技術採択と学習」をテーマに構造推定を試みているもので、 (i) どのような枠組みでどのように構造推定をしようとしているのか、 (ii) 同時期に出版された、同様に「技術採択と学習」をテーマにしているFoster and Rosenzweig (1995)とどのように違うのか、をまとめてみたいと思いこの論文を選びました。
第一回は経済学界の流れ、2回目は理論の話だったので、今回は実証側の話をタイムリーなトピックと絡めてしようと思います。筆者は北カリフォルニア在住なのですが、アメリカ西海岸では2020年8月中旬から1ヶ月ほど山火事が続き、2万平方メートル(おおよそ四国ぐらい)以上の土地が燃えたとのことです。山火事は毎年この時期になると西海岸の各地で発生するのですが、近年の山火事のペース、そのなかでも今年の発生数が突出していることがこちらの記事などでわかると思います。
今日は、UBCのBranderさんとカルガリー大のTaylorさん(以下BT)のAER論文”The Simple Economics of Easter Island: A Ricardo-Malthus Model of Renewable Resource Use”について話したいと思います。 論文はこちらからダウンロードできます。
今日は掲題の論文について話したいと思います。 論文はこちらから。